【図工鑑賞】鳥獣戯画~『倒れた蛙』の謎~
.
図工の製作がひとまず終わり、秋のイベントも一息ついたので、まったりと図工の鑑賞。
図工の鑑賞授業は、何度やっても飽きないくらい好きで、子どもも
「またやろう!」
と必ず言ってくれる。
なぜなら、他の教科(とくに算数)とは違って、完全に
「言ったもの勝ち」
だからだろう。
好きなことを言えるし、そのことを認めるしかない、という構造。
不確定なものを、不確定な脳で、わいわいと言い合うだけ。
他と競争したり、張り合う必要はない。
自分の脳みそが、なんでこう働くのだろうか、と不思議になってくる。
ある種の、セラピーのようなもの、かもしれない。
(まあ、言う人に言わせれば、子どもの遊びはほとんどがセラピーらしいが)
鳥獣戯画、という有名な絵巻物。
これが、小学生にはずいぶん人気で、
「かっわいいいーーーー」
である。
これが平安時代のものだ、というと、しばらくみんな無言になる。
なんでこんなかわいいセンスが当時にあったのか、とみんな驚くが、実は日本人はこの感性を失わないまま、ずっと現代まで生き続けている、というのが実際なんだろう。

鳥獣戯画のある個所に、『倒れた蛙』がいる。
クラスで鑑賞していくうち、このカエルに焦点が当たった。
「ぼくは、このカエルは猿に殺されたと思います」
という子がいる。
「ぼくも」
と賛成意見が多数。
みんな、この絵のつづき、右側にいる、逃げた猿に注目し、関連を考えたらしい。
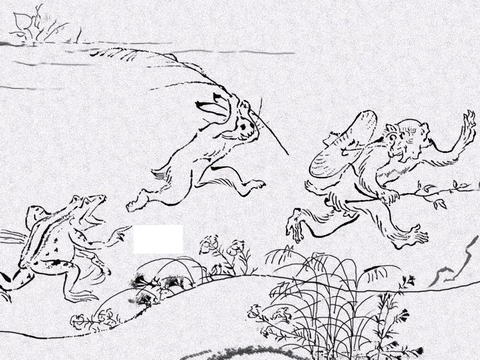
「わたしは、猿が持っていた、するどい茎の先で、ぶすっと蛙のお腹を突き刺して、殺したんだと思う。山から下りてきた猿が、強盗をはたらいたんだと思う」
クラスで一番おとなしい女の子がこういうことを言うので、がぜん盛り上がってくる。
殺し
強盗
こんな単語が、教室の中をやすやすと飛び交うため、ちょっと私は気が咎めるが、仕方がない。
ところが、これを「殺し」だとは思わない子もいる。
「えー、ぼくは殺したんじゃなくて、ただ転ばせたんだと思う。ふざけて足を引っかけたかなにかで・・・。その証拠に、倒れた蛙のまわりにいる狐とか、あんまり驚いてないし、むしろ笑ってるみたいだから」
ふむふむ。
たしかに、殺しだとすれば、もっと状況が殺伐とするか、非常事態だ、という緊迫した雰囲気が出るかも。
絵をみるかぎり、なんともほんわかとした平和な空気が流れている。
これは、『殺し』じゃ、ないかもな。
ここまでくると、そもそも鳥獣戯画の他の場面で、こうした殺伐とした事件を扱っているだろうか、と疑問が出てくるので、せっかくだから、と「甲の巻」をぜんぶ見た。
ところが、ここ以外は、ほとんど、のほほーん、とした空気である。
「殺人の意見を撤回します」
殺された、という刑事ドラマのような見立てをした女の子が、意見を取り消した。
そこで、新たな意見が。
「これ、酔っ払って倒れてるんじゃないの?」
なるほど。
そうかもな。
「だって、烏帽子をかぶったおじいさんの蛙とネコの左側で、蛙が里芋の葉をかぶって田楽踊りをしてる」
どれどれ、とみんなで確認。

そうだ。
これ、マツリだ。
みんな、お祭りに来てるんだ。
この烏帽子のネコが、人目を忍んできている風なのも、おそらくふだんはこんな場所にはこない位の高い貴族が、お祭りだからと久しぶりに外に出てきたんだろう。
お祭りなら、酔っ払っているのも分かるなあ。
だけど、じゃあ、なんで猿が逃げてるの?
ここで、ふだん、冗談ばかり言っている男の子が、
「カエルが、ひっくりカエルで、サルは、去る、ということじゃないの?」
あ~
だじゃれかよっ!
(ただ、それだけのことか!?)
図工の製作がひとまず終わり、秋のイベントも一息ついたので、まったりと図工の鑑賞。
図工の鑑賞授業は、何度やっても飽きないくらい好きで、子どもも
「またやろう!」
と必ず言ってくれる。
なぜなら、他の教科(とくに算数)とは違って、完全に
「言ったもの勝ち」
だからだろう。
好きなことを言えるし、そのことを認めるしかない、という構造。
不確定なものを、不確定な脳で、わいわいと言い合うだけ。
他と競争したり、張り合う必要はない。
自分の脳みそが、なんでこう働くのだろうか、と不思議になってくる。
ある種の、セラピーのようなもの、かもしれない。
(まあ、言う人に言わせれば、子どもの遊びはほとんどがセラピーらしいが)
鳥獣戯画、という有名な絵巻物。
これが、小学生にはずいぶん人気で、
「かっわいいいーーーー」
である。
これが平安時代のものだ、というと、しばらくみんな無言になる。
なんでこんなかわいいセンスが当時にあったのか、とみんな驚くが、実は日本人はこの感性を失わないまま、ずっと現代まで生き続けている、というのが実際なんだろう。

鳥獣戯画のある個所に、『倒れた蛙』がいる。
クラスで鑑賞していくうち、このカエルに焦点が当たった。
「ぼくは、このカエルは猿に殺されたと思います」
という子がいる。
「ぼくも」
と賛成意見が多数。
みんな、この絵のつづき、右側にいる、逃げた猿に注目し、関連を考えたらしい。
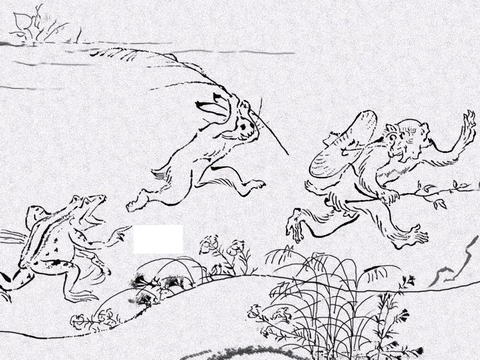
「わたしは、猿が持っていた、するどい茎の先で、ぶすっと蛙のお腹を突き刺して、殺したんだと思う。山から下りてきた猿が、強盗をはたらいたんだと思う」
クラスで一番おとなしい女の子がこういうことを言うので、がぜん盛り上がってくる。
殺し
強盗
こんな単語が、教室の中をやすやすと飛び交うため、ちょっと私は気が咎めるが、仕方がない。
ところが、これを「殺し」だとは思わない子もいる。
「えー、ぼくは殺したんじゃなくて、ただ転ばせたんだと思う。ふざけて足を引っかけたかなにかで・・・。その証拠に、倒れた蛙のまわりにいる狐とか、あんまり驚いてないし、むしろ笑ってるみたいだから」
ふむふむ。
たしかに、殺しだとすれば、もっと状況が殺伐とするか、非常事態だ、という緊迫した雰囲気が出るかも。
絵をみるかぎり、なんともほんわかとした平和な空気が流れている。
これは、『殺し』じゃ、ないかもな。
ここまでくると、そもそも鳥獣戯画の他の場面で、こうした殺伐とした事件を扱っているだろうか、と疑問が出てくるので、せっかくだから、と「甲の巻」をぜんぶ見た。
ところが、ここ以外は、ほとんど、のほほーん、とした空気である。
「殺人の意見を撤回します」
殺された、という刑事ドラマのような見立てをした女の子が、意見を取り消した。
そこで、新たな意見が。
「これ、酔っ払って倒れてるんじゃないの?」
なるほど。
そうかもな。
「だって、烏帽子をかぶったおじいさんの蛙とネコの左側で、蛙が里芋の葉をかぶって田楽踊りをしてる」
どれどれ、とみんなで確認。

そうだ。
これ、マツリだ。
みんな、お祭りに来てるんだ。
この烏帽子のネコが、人目を忍んできている風なのも、おそらくふだんはこんな場所にはこない位の高い貴族が、お祭りだからと久しぶりに外に出てきたんだろう。
お祭りなら、酔っ払っているのも分かるなあ。
だけど、じゃあ、なんで猿が逃げてるの?
ここで、ふだん、冗談ばかり言っている男の子が、
「カエルが、ひっくりカエルで、サルは、去る、ということじゃないの?」
あ~
だじゃれかよっ!
(ただ、それだけのことか!?)